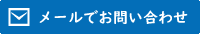兼務役員に就任したとき

兼務役員に就任した社員がいます。
労務管理上の位置づけや、労働者としての扱い、給与や社会保険の取り扱いなど、どのようになりますか?

兼務役員とは、会社の役員でありながら、従業員としての業務にも従事している者を指します。
たとえば、部長や工場長、店長などの職務を担いながら、取締役などの役員に就任しているケースが該当します。
■ 労務管理上の位置づけ
兼務役員は、形式上は役員であるものの、実態として従業員と同様の業務に従事している場合は、労働者としての側面も併せ持ちます。
したがって、労働者性の有無は、実際の勤務実態(指揮命令関係、勤務時間の拘束、賃金の支払い方法など)により判断されます。
■ 労働者としての扱い(雇用保険・労災保険)
【雇用保険】
原則として、役員は雇用保険の被保険者にはなれません。
しかし、以下のすべての要件を満たす兼務役員であれば、雇用保険の被保険者となることが可能です。
- 代表権や業務執行権を持っていない
- 就業規則が適用され、勤怠管理がされている
- 役員報酬よりも従業員としての給与が多い
必要な添付資料には、労働者名簿、出勤簿、賃金台帳、雇用契約書、就業規則、定款、登記事項証明書、決算書の役員報酬明細などがあります。
【労災保険】
原則として役員は労災保険の適用外です。
しかし、兼務役員であれば労働者としての業務に従事している実態がある場合、労災保険の対象となります。
年度更新時には「役員で労働者扱いの人」として、役員報酬を除いた賃金を集計し、労災保険料を算出します。
■ 給与の取り扱い
兼務役員に支払われる報酬は、以下の2つに分けて管理する必要があります。
- 役員報酬:取締役等の役員としての報酬。労働保険料の算定対象外。
- 給与(賃金):従業員としての業務に対する給与。労働保険料の算定対象。
■ 社会保険(健康保険・厚生年金保険)
社会保険については、すでに被保険者である従業員が役員に就任した場合、引き続き被保険者となるため、特段の手続きは不要です。
以上のように、兼務役員は「役員」と「労働者」の両面を持つため、
実態に応じた適切な労務管理と保険手続きが求められます。
給与の区分管理や保険料の算定においては、役員報酬と従業員給与を明確に分けて取り扱うことが重要です。